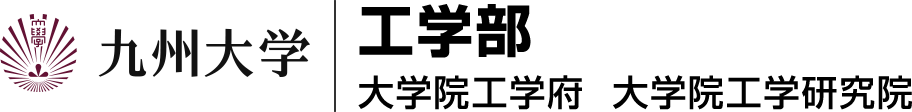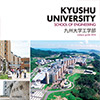留学体験談(動画)
2024年12月実施 『工学系学生のための海外留学フェア』 アーカイブ動画
(香港科技大学、バンドン工科大学(インドネシア)の留学体験談)
2025年11月実施 『工学部海外留学報告会』 アーカイブ動画
(ワシントン大学(米国)、ルンド大学(スウェーデン)の留学体験談)
海外インターンシップ 体験記
楠見 健太郎(工学部電気情報工学科4年)
インターンシップ先:NXPセミコンダクターズ
派遣期間:2022年8月~2023年7月

山を背景に線路のそばで撮っている写真: 休日に思いつきで行った小旅行で、ふらっと降りた駅の近くで撮った写真。アルプスの山々が綺麗でした
大学入学前からサイバーセキュリティ分野に興味があり、現在は工学部電気情報工学科でこの分野に取り組んでいます。
IAESTEへは2021年の秋(2年次)に応募し、選考を経て冬前に派遣候補生になりました。翌年7月に無事派遣が決まり、バタバタの中8月にオーストリアへ渡航しました。派遣先のNXPセミコンダクターズは文字通り半導体を開発する会社で、その中で、クレジットカードなどICカードに乗せられるICチップ向けのソフトウェアを開発する部署へ派遣されました。サイバーセキュリティに興味があった私としては、セキュリティが特に重視される開発部署への派遣はまさに願ったり叶ったりでした。

ディナーパーティー: インターンシップが終わる時、グラーツ支社所属のチームメンバーにご飯に連れて行ってもらったときの写真。1年間とてもお世話になり、またパーティーまで開いてもらって本当に嬉しかったです
渡航前は英語力、とりわけ話す能力に自信がなく、現地の公用語がドイツ語というのも相まって、コミュニケーションができるかがとても不安でした。しかし、いざ実際に働き始めてみると、自己管理などの方がむしろ大変で、コミュニケーションは全然問題なかったです。周りの方々が優しくて、案外気兼ねなく話すことができました。最終的には、プロジェクトマネージャーから成長したねと太鼓判を押してもらえるほど、英語については不自由なく会話できるようになりました。会社の外では音楽の都ウィーンへオペラを観に行ったり、各所の地ビールを飲み比べに行ったり、部署での川下りイベントなどに参加したりと、充実した生活を過ごせました。
派遣を通じ、英語力が上がったり、より実際的な知識を得られたり、友人を作れたりと、視野がぐんと広がりました。なにより、派遣前は曖昧だった自分の進路について、より明確になり魅力的に感じられるようになりました。1年休学しての経験でしたが、その価値が十二分にあったと強く思います。海外インターンシップの経験は、人生を左右しうる、なかなか勇気のいる決断だと思いますが、ぜひ恐れず挑戦してみてください!

勤務最終日に看板の前でビール片手に撮ってもらった写真。達成感と、寂しさと、やっと日本に帰れる嬉しさが混ざった不思議な感覚でした

ウィーンの友人に観光に連れて行ってもらったときの写真。ウィーンの街並みは建築様式がとても綺麗でした
日本からたった一歩、されど大きな一歩
岡野 翔大 (工学府土木工学専攻1年)
留学先:国立台湾大学
派遣期間:2023年8月~2025年1月
 私は修士1年の夏からダブルディグリープログラムを利用して国立台湾大学に留学し、地盤工学を専攻しています。
私は修士1年の夏からダブルディグリープログラムを利用して国立台湾大学に留学し、地盤工学を専攻しています。
もともと、外国と比較した日本の産業の強みについて外からの視点で知りたいという思いがあり留学を希望していました。しかし、ちょうどその時期がコロナ禍と重なり、学部では留学することができませんでした。修士に進学するタイミングで研究の担当教員から留学の話を聞き、これはまたとない貴重なチャンスだと考え、留学することを決めました。
国立台湾大学は台湾北部の台北市に位置し、福岡からわずか2時間ほどで到着します。この立地の利点は欧米の大学と比較しても大きいと思います。例えば、工学部の学生は卒業の1年半前の夏休みに就職活動の一環として長期インターンシップに行くことが一般的ですが、台湾からなら問題なく参加でき、さらに留学中の経験もアピールできます。
 国立台湾大学の土木工学科ではすべての授業が英語で行われており、学生は英語が非常に堪能です。中国語の能力不足による問題は全くありませんでしたが、初めのうちは自分の発音(いわゆるカタカナ英語)に自信がありませんでした。しかし、ベトナムやインドネシアなどから来た留学生が自国のアクセントで堂々と話しているのを見て、発音の綺麗さではなく態度が重要だと気付き、自信をもって意見を述べられるようになりました。その結果、海外の学会に台湾大学代表として参加したときにはタイの大学の教授から「あなたの研究はとても興味深く、何より発表が良かった。これからも頑張ってください」と褒められました。
国立台湾大学の土木工学科ではすべての授業が英語で行われており、学生は英語が非常に堪能です。中国語の能力不足による問題は全くありませんでしたが、初めのうちは自分の発音(いわゆるカタカナ英語)に自信がありませんでした。しかし、ベトナムやインドネシアなどから来た留学生が自国のアクセントで堂々と話しているのを見て、発音の綺麗さではなく態度が重要だと気付き、自信をもって意見を述べられるようになりました。その結果、海外の学会に台湾大学代表として参加したときにはタイの大学の教授から「あなたの研究はとても興味深く、何より発表が良かった。これからも頑張ってください」と褒められました。
 また、私が台湾での留学で得た最も価値のあるものは、研究室の友人たちです。彼らは外国人である私を特別扱いせず、よく食事や遊びに連れて行ってくれます。ほとんどのお店が閉まる旧正月の時期には、実家に招待して台湾の伝統的な食事をふるまっていただいたこともありました。彼らとは文化や価値観は異なりますが共通の目標である研究や学業を通じて結びついています。彼らとの交流を通じて、異なる文化や価値観を理解することができ、自分自身も成長することができたと感じています。
また、私が台湾での留学で得た最も価値のあるものは、研究室の友人たちです。彼らは外国人である私を特別扱いせず、よく食事や遊びに連れて行ってくれます。ほとんどのお店が閉まる旧正月の時期には、実家に招待して台湾の伝統的な食事をふるまっていただいたこともありました。彼らとは文化や価値観は異なりますが共通の目標である研究や学業を通じて結びついています。彼らとの交流を通じて、異なる文化や価値観を理解することができ、自分自身も成長することができたと感じています。


留学で得たもの
小澤 翼 (工学部機械航空工学科 航空宇宙工学コース)
留学先:シンガポール国立大学
派遣期間:2019年8月~2020年3月
 私は学部3年生の夏から約1年間シンガポール国立大学へ留学していました。学習・私生活がともに充実した最高の時間を過ごせました。今でもCNA(シンガポールの国営メディア)ラジオでシンガポールの渋滞情報を聞くと馴染みある道の名前がたくさん登場し、懐かしい思いが込み上げてきます。
私は学部3年生の夏から約1年間シンガポール国立大学へ留学していました。学習・私生活がともに充実した最高の時間を過ごせました。今でもCNA(シンガポールの国営メディア)ラジオでシンガポールの渋滞情報を聞くと馴染みある道の名前がたくさん登場し、懐かしい思いが込み上げてきます。
シンガポールでの生活で特別だったことを挙げるとするならば、まず真っ先に思いつくのが友人です。特に人工衛星の授業を一緒に受講し、設計コンペにも出場した現地生の友人は寮が同じだったこともあり、今でもZoomで時々話します。彼とはほぼ毎朝ランニングに一緒に行き、お互いが所属する団体の運営方法など身近なテーマから政治・歴史・人生の価値観についてなど、様々なことを話しました。互いに異なる主張をすることもしばしばでしたが、何か大きな国際ニュースがあるたびに ”What do you think ?” と聞かれ、真っ向から意見が衝突することがあっても、それを是とできる関係は非常に心地よく刺激的であると感じました。また、現地で出会った交換留学生の日本人の中で生涯にわたって付き合いが続くであろう大切な友人に出会えました。留学は普段の環境とは違った属性の人たちと巡り合い、彼ら彼女らと関係を築く絶好の機会だと思います。
 また、留学を通して得たスキル(?)について考えると、3つのものが挙げられます。まず一つ目は英語で行うプロジェクトでも「なんとかなる」と思えるようになったことです。私の当初の留学計画ではコロナがなければ現地の人工知能を扱う研究所でインターンをする予定でした。ある日私が送った応募メールへ「明日オフィスに来れるか?」という返事が来て面接に行ったのですが、勉強不足のまま面接に臨むことになり人生で一番脂汗をかいた30分を過ごしました。研究所の開発プロジェクトのマネージャーたちから矢継ぎ早にくる質問に対して冷や汗をかきながら拙い英語で返事を必死に考えました。その後受け入れが決まるもコロナで帰国が決まり、そのインターンには行けませんでしたが面接だけでも良い経験になったと思います。また、先述の人工衛星のコンペではチームリーダーとして出場名簿に自分の名前を記録しました。しかしメンバーたちと会議を開いて話し合いが始まり議論が盛り上がってくると、訛りが入ったスピーディーな英語についていけなくなり基本的にオブザーバーのような立ち位置になってしまうことが多々ありました。これについては最後まで克服することはできませんでしたが、少しでも自分の存在感を出そうと人工衛星についての勉強は捗りました。したがって、コンペへの参加を通して専門性と語学力が向上したことは間違いありません。以上のように、留学を通してなんとかなる(する)力・専門性・語学力の3つが向上したと思います。
また、留学を通して得たスキル(?)について考えると、3つのものが挙げられます。まず一つ目は英語で行うプロジェクトでも「なんとかなる」と思えるようになったことです。私の当初の留学計画ではコロナがなければ現地の人工知能を扱う研究所でインターンをする予定でした。ある日私が送った応募メールへ「明日オフィスに来れるか?」という返事が来て面接に行ったのですが、勉強不足のまま面接に臨むことになり人生で一番脂汗をかいた30分を過ごしました。研究所の開発プロジェクトのマネージャーたちから矢継ぎ早にくる質問に対して冷や汗をかきながら拙い英語で返事を必死に考えました。その後受け入れが決まるもコロナで帰国が決まり、そのインターンには行けませんでしたが面接だけでも良い経験になったと思います。また、先述の人工衛星のコンペではチームリーダーとして出場名簿に自分の名前を記録しました。しかしメンバーたちと会議を開いて話し合いが始まり議論が盛り上がってくると、訛りが入ったスピーディーな英語についていけなくなり基本的にオブザーバーのような立ち位置になってしまうことが多々ありました。これについては最後まで克服することはできませんでしたが、少しでも自分の存在感を出そうと人工衛星についての勉強は捗りました。したがって、コンペへの参加を通して専門性と語学力が向上したことは間違いありません。以上のように、留学を通してなんとかなる(する)力・専門性・語学力の3つが向上したと思います。
 現在私は航空宇宙工学科の研究室に所属し、オーストラリアの共同研究先と人工衛星のエンジンの開発に取り組んでいます。そういった事情からミーティングや研究報告も英語で行っています。そうした中で、九大に入学した時と比べると「日本と海外」という境界線が格段にボーダーレスになってきているのを感じます。まだまだ専門性も語学力もひよっこですが、着実に進歩しているとは思います。その中で交換留学が果たした役割はとてつもなく大きいです。少しでも興味のある方は学部生のうちに一度交換留学を経験されることをお勧めします!
現在私は航空宇宙工学科の研究室に所属し、オーストラリアの共同研究先と人工衛星のエンジンの開発に取り組んでいます。そういった事情からミーティングや研究報告も英語で行っています。そうした中で、九大に入学した時と比べると「日本と海外」という境界線が格段にボーダーレスになってきているのを感じます。まだまだ専門性も語学力もひよっこですが、着実に進歩しているとは思います。その中で交換留学が果たした役割はとてつもなく大きいです。少しでも興味のある方は学部生のうちに一度交換留学を経験されることをお勧めします!
学位留学の価値を実感した3年間
笠井 蒼生 (工学部地球環境工学科卒業)
留学先:ルンド大学(スウェーデン)
派遣期間:2019年8月~2022年1月(途中、新型コロナウィルスの影響により一時帰国期間あり)
 修士課程では、都市環境システム工学を専攻し、ダブルディグリープログラムを利用してスウェーデンのルンド大学に学位留学しました。ルンド大学では、実際のフィールドを対象としたプロジェクトワークを主に取り組み、豪雨や地下水の解析など幅広い水理学の知識を実践的に学ぶことができました。
修士課程では、都市環境システム工学を専攻し、ダブルディグリープログラムを利用してスウェーデンのルンド大学に学位留学しました。ルンド大学では、実際のフィールドを対象としたプロジェクトワークを主に取り組み、豪雨や地下水の解析など幅広い水理学の知識を実践的に学ぶことができました。
学部課程では、イギリスのケンブリッジに短期留学をする機会があり、その際に海外により長期滞在することで、日本を外から見つめてみたいと思うようになりました。学位留学はコロナ禍ではありましたが、多様な国籍・背景を持った先生方や生徒と実際に対面で交流することができ、日本との文化や価値観の違いを直に感じることが出来ました。
留学には自身の価値観を大きくアップデートするチャンスが潜んでいます。言語の壁を乗り越えて、現地でやり遂げた事には多くの達成感を得られるはずです。皆さんの大学生活が実り多きものでありますように。