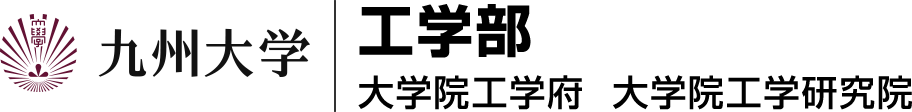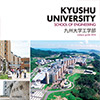住宅から都市に至る人間の多様な生活に密着した空間を造り出す建築家や技術者、研究者を養成
 建築は使いやすく快適で、美しくて、しかも丈夫でなければなりません。建築学は、技術的問題から社会的・文化的問題にまで及ぶ極めて広い領域にかかわっており、建築・都市の分野に携わる者は、これらの多様な要素を総合的にまとめあげてゆく能力が必要とされます。そして、総合的な技術・知識の理解が要求されるばかりでなく、芸術的な造形能力も求められます。建築学科では、住宅から都市に至る人間の多様な生活に密着した空間をつくり出すために、建築・都市の文化を歴史的に顧みながら、建築・都市を理論的に計画し、具体的な形に設計する方法、快適・健康な環境をつくり出すための環境工学、壊れない建物をつくるための建築構造技術、建築を構成する材料とその施工技術などについて教育・研究を行っています。
建築は使いやすく快適で、美しくて、しかも丈夫でなければなりません。建築学は、技術的問題から社会的・文化的問題にまで及ぶ極めて広い領域にかかわっており、建築・都市の分野に携わる者は、これらの多様な要素を総合的にまとめあげてゆく能力が必要とされます。そして、総合的な技術・知識の理解が要求されるばかりでなく、芸術的な造形能力も求められます。建築学科では、住宅から都市に至る人間の多様な生活に密着した空間をつくり出すために、建築・都市の文化を歴史的に顧みながら、建築・都市を理論的に計画し、具体的な形に設計する方法、快適・健康な環境をつくり出すための環境工学、壊れない建物をつくるための建築構造技術、建築を構成する材料とその施工技術などについて教育・研究を行っています。
 本学科のカリキュラムは、建築学に関わる諸知識を体系的・理論的に学ぶための講義科目、具体的なデザイン手法を習得するための設計演習科目、専門的知識を体得するための演習・実験科目などがバランスよく組み込まれ、充実した内容となっています、このような教育を通じて、工学的技術や建築文化についての幅広い教養を修得し、国際社会の第一線で活躍する建築家や技術者、研究者を養成します。
本学科のカリキュラムは、建築学に関わる諸知識を体系的・理論的に学ぶための講義科目、具体的なデザイン手法を習得するための設計演習科目、専門的知識を体得するための演習・実験科目などがバランスよく組み込まれ、充実した内容となっています、このような教育を通じて、工学的技術や建築文化についての幅広い教養を修得し、国際社会の第一線で活躍する建築家や技術者、研究者を養成します。
先輩インタビュー
Q1 あなたが九州大学工学部および在籍している学科を選んだ理由を教えてください。
私が九州大学工学部建築学科を選んだのは、高校時代に訪れた校舎の建物に強く心を惹かれたことがきっかけでした。光の入り方や空間の広がり方、素材の使い方など、ただ「使うための建物」ではなく、人の心を動かす力を持った建築に出会い、「いつか自分もこんな建築を設計してみたい」と思うようになりました。九州大学の建築学科は、設計やデザインだけでなく、構造や環境、材料といった幅広い分野から建築を学べるのが大きな魅力です。また、実務経験のある先生方から直接学べる環境も整っており、現実の建築に根ざした学びができる点にも惹かれました。多様な価値観を持つ仲間たちと刺激し合いながら、自分の「つくりたい」という思いを少しずつ形にしていける場として、九州大学の建築学科はとても魅力的な場所だと感じています。
Q2 あなたが在籍している学科について、どのような点に魅力を感じていますか?
私が在籍している九州大学工学部建築学科の魅力は、まず、実務経験の豊富な建築家の先生方から直接学べる環境が整っていることです。実際のプロジェクトに携わってきた先生方が、設計の考え方や現場のリアルな話を交えながら授業をしてくださるため、教科書だけでは得られない“生きた知識”を学ぶことができます。また、授業の種類がとても豊富で、デザインや構造、環境、都市計画など幅広い分野を自分の関心に合わせて深めていけるのも大きな魅力です。設計演習では、自分のアイデアを形にするプロセスをじっくり学ぶことができ、先生方からの丁寧なフィードバックを通じて成長を実感できます。理論と実践のバランスが取れたカリキュラムの中で、建築を多角的にとらえる力を養えるこの学科は、建築を本気で学びたい人にとってとても魅力的な場所だと思います。
Q3 あなたが所属する研究室名、そこで行っている研究内容について高校生にわかるように教えてください。
研究室(教授)名:建築デザインエンジニアリング学研究室(末光 弘和 教授)
研究内容:私たちの研究室では、「建築をつくる材料」と「建物をとりまく環境」の2つのテーマに取り組んでいます。たとえば、牡蠣の殻を使ったコンクリートや、土・菌糸体・火山灰など、自然素材を活かした新しい建築材料の研究を行っています。身のまわりにある“当たり前”の素材が、実は建築にどんな可能性を秘めているのかを探るのは、とてもおもしろく、やりがいのある挑戦です。また、建物の中やまわりを流れる風、熱の動きといった「環境」の研究も行っており、暮らしをより快適に、持続可能にするヒントを見つけ出そうとしています。自分の手で実験や観測を行い、発見する楽しさを味わえるのが、研究の大きな魅力です。
Q4 将来の夢を教えてください。
私の将来の夢は、自然素材を利用した建築空間の設計を行う建築家になることです。コンクリートや鉄骨が普及したここ数十年、建物から自然が消え殺風景で均質的な空間が当たり前になりつつあります。そこで私は、現在研究を行っている自然素材の特性を活かした空間を設計しこれまでにない建築の在り方を模索する建築家になりたいです。