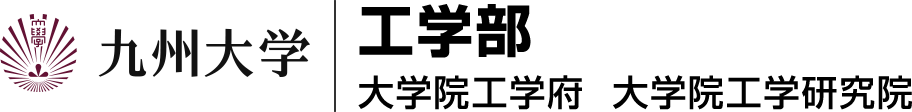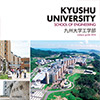造船技術の発展と持続的な海洋開発を担い,海と人類の共生に貢献できる技術者・研究者への扉
 国土を海洋に囲まれた我が国の将来の発展には,社会・生活を支えるエネルギー・資源の調達や生産物の供給のための海上輸送,海洋資源開発,食糧生産等の海洋の有効利用が必要になります。
国土を海洋に囲まれた我が国の将来の発展には,社会・生活を支えるエネルギー・資源の調達や生産物の供給のための海上輸送,海洋資源開発,食糧生産等の海洋の有効利用が必要になります。
本学科では海洋の有効利用のための技術修得を目的に,工学基礎である構造,流体,熱,材料,制御などの幅広い技術分野を修学するだけでなく,巨大な船や海洋構造物を実際に設計・建造し統合化してゆくための総合工学を身に付けられるように特色あるカリキュラムを編成しています。
 カリキュラムの中には,多面的に実物を見るために,造船工場や製鉄所見学,3年次の工場実習を用意しています。また,自ら大型船を設計し,その図面を一通り描き上げる設計演習も組み入れています。一方,船や海洋構造物の計画・設計,生産管理には情報技術の利用が不可欠であることから,プログラミング,数値解析・シミュレーション,コンピュータ支援設計,AI・機械学習に関する教育も取り入れています。
カリキュラムの中には,多面的に実物を見るために,造船工場や製鉄所見学,3年次の工場実習を用意しています。また,自ら大型船を設計し,その図面を一通り描き上げる設計演習も組み入れています。一方,船や海洋構造物の計画・設計,生産管理には情報技術の利用が不可欠であることから,プログラミング,数値解析・シミュレーション,コンピュータ支援設計,AI・機械学習に関する教育も取り入れています。
本学科の卒業生への評価は高く,就職時の求人数は卒業生の数を大幅に上回り,学生は各自が希望する輸送機器,重機・重工業の他,多様な業種の企業および研究機関等に就職しています。また,多くの学生が大学院修士課程,博士後期課程に進学して,より高度な勉学と研究に励んでいます。
先輩インタビュー
Q1 あなたが九州大学工学部および在籍している学科を選んだ理由を教えてください。
私がこの学科を志望した理由は、専門的に船舶の設計に関する学習を行うことができるからです。もともと造船に興味があったため、そのために必要な知識を学べるという点や3年次に1年かけて実際に設計を行ってみるというカリキュラムが組まれている点を大変魅力的に感じ志望しました。
Q2 あなたが在籍している学科について、どのような点に魅力を感じていますか?
全国でも数少ない、船舶の設計を専門的に学べる学科である点です。中でも、3年次には1年間かけて船舶を1隻設計するというカリキュラムが組まれており、その演習の中でそれまでに学習してきたことの復習をしながら造船についての知見を深めることができる点は他の大学や学科にはない魅力だと思います。また、船舶は様々な学問の集大成であるため、船舶について学習していく中で力学から機械学習まで、複数の分野を学習していくことができます。研究においても造船を対象にした研究室はもちろん、洋上風力発電や溶接を対象とした研究室も存在しており、様々な分野の研究を行うことができます。加えて、洋上風力発電などの技術者から話を聞きながら進路を考えていくことができます。学科内のつながりについても、学科内での行事が多数開催されており、上級生・下級生はもちろん先生方も身近な存在である点も魅力と感じています。
Q3 あなたが所属する研究室で行っている研究内容について高校生にわかるように教えてください。
研究室(教授)名:船舶海洋運動制御工学研究室 (古川 芳孝 教授)
研究内容:船舶の運動は、船の形状が違う場合は当然として、同一の形状であったとしても、風や潮流・波等の外乱、水深や水路や岸壁の形状などにより変わってきます。また、これらが異なる場合に船舶の運動へと与える影響はとても複雑でいまだわかってない部分もあります。当研究室においては長さ38.8m、幅24.4m、水深2mの巨大な試験水槽を用いて行う実験やコンピューターシミュレーションを利用して船の運動を推定・評価する研究をしています。近年では、これまでの研究で得た知見を生かして船舶の自動航行に関する研究も行っています。
Q4 将来の夢を教えてください。
周囲を海に囲まれた日本では、これから発展をしていくためにはもちろん、日々の生活を快適に過ごすためにも船舶を活用することが必須です。また、地球温暖化などの問題が大きくなっていく中で、その解決に向けて船舶業界が果たすべき役割も大きくなっています。自身が学習した船舶の知識を活用して、技術者としてその一助を担うことが私の夢です。