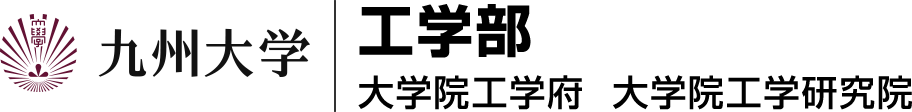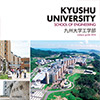サステナブルで豊かな国土や都市を構築するための技術を学ぶ

上西郷川の再生プロジェクト。洪水が頻発していた川の改修において、治水対策と同時に自然環境の再生を実現し、2016年土木学会デザイン賞最優秀賞を受賞しました。
土木工学は、私たちが安全・安心で豊かな暮らしを営むために必要となる国土の基盤(都市、道路、河川、海岸、山林など)を整備・保全するための幅広い学問です。頻発する災害に対する防災技術、人工的な都市と自然や生態系との調和を目指すグリーンインフラ、ビッグデータを使った次世代型の交通サービス、耐久的な構造物を構築するための新素材の開発なども土木工学の分野です。
土木技術は人類の歴史とともに発展してきました。道路、橋、上下水道、鉄道、港などによって現代の社会は成り立っています。世界ではいま、環境・社会・経済の問題が山積しています。土木工学は、伝統的な技術を継承・発展させるとともに、最先端の技術(AI、自動運転、5Gなど)を取り入れながら、50年後、100年後、その先の未来を見据えた持続的で豊かな国土や都市を構築していきます。

スーパーコンピューターによる津波シミュレーション。VR(仮想現実)を用いたバーチャル避難体験などの啓蒙活動や,避難計画の立案に活用されています。
変化の激しい世の中で、さまざまな技術やアイディアを結びつけ、国内・国外を問わず、それぞれの地域で市民の暮らしを豊かにできる土木技術者(Civil engineer)が必要とされています。土木工学科では、卒業後に第一線でCivil engineerとして活躍できるよう、専門知識だけでなく、マネジメント力、コミュニケーション能力、リーダーシップ、倫理観を養うことができます。
先輩インタビュー
Q1 あなたが九州大学工学部および在籍している学科を選んだ理由を教えてください。
私は高校生のころ、物理や化学、生物や社会などいろいろな科目に興味があったため進路を迷っていました。そのような中で、多くの科目が関係している土木工学について知り、魅力を感じました。加えて、各地で災害が発生する状況を見て、防災に関することを学びたいと思い、土木工学科を選択しました。
Q2 あなたが在籍している学科について、どのような点に魅力を感じていますか?
様々な専門科目を学べることが魅力だと感じています。基本となる構造力学・地盤力学・水理学をはじめとして、材料(コンクリート・鋼構造)・環境(生態系・循環型社会・上下水道・河川・海岸)・計画(都市計画・交通・景観)・地震・気象など多岐にわたる分野を勉強することができるため、興味のある科目がきっと見つかると思います。
また、座学だけではなく実験・実習やフィールドワークも豊富です。特に、学部3年生の後期にはグループで橋の設計から製作まで行ったり、実際の地域課題に対する施策を自分たちで検討したりする授業があり、実践的な学びを得ることができます。
さらに、学部3年生の6月から9月は、授業がない代わりにインターンシップや留学、調査や土木構造物の見学などといった活動を自分で計画して実施するサマープログラムという期間になっています。自分の興味のある分野について深堀りしたり、大学を飛び出して学問と社会のつながりを体感したりすることができる、九大土木ならではのプログラムだと思います。
Q3 あなたが所属する研究室で行っている研究内容について高校生にわかるように教えてください。
研究室(教授)名:水圏環境工学研究室(広城 吉成 准教授 /Lagrosas Nofel 准教授 /西山 浩司 助教)
研究内容:私の所属する研究室では、水循環や気象・大気環境に関する研究を行っています。具体的には地下水環境や棚田の防災機能の解析、ニューラルネットワークを用いた線状降水帯の発生診断・予測、リモートセンシング(衛星データ)を用いた大気環境の解析などを行っています。
私はまだ研究室に配属されたばかりですが、古文書の記述から、過去(江戸時代など)に発生した線状降水帯や豪雨災害をデータにし、現代や将来の気象防災につなげる研究に取り組みたいと考えています。
Q4 将来の夢を教えてください。
近年、インフラの老朽化や激甚化する災害などが問題となる中、土木が果たす役割は大きいと感じています。具体的な進路はまだ決まっていませんが、大学で得た経験や学んだ知識を活かし、課題の解決に貢献したいと考えています。